放課後子ども教室
佐野市教育委員会では、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するため、放課後子ども教室を実施しています。
放課後子ども教室とは、放課後や週末等に学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等、様々な活動を実施する事業です。
放課後子ども教室と放課後児童クラブの違い
| 内容 | 放課後子ども教室 | 放課後児童クラブ |
|---|---|---|
| 目的 | 安全・安心な子どもの活動拠点(居場所)として、体験活動やスポーツ、地域住民との交流活動等の機会を提供する。 | 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童へ、放課後の遊び、生活の場を提供し、健全育成を図る。 |
| 法的位置づけ | なし(社会教育事業) | 児童福祉法第6条の3第2項に規定された社会福祉事業 |
| 対象児童 | 全ての小学生 | 放課後、保護者が就労等により留守にする家庭の小学生 |
| スタッフ | コーディネーター、協働活動サポーター等の地域ボランティア | 放課後児童支援員(有資格)、補助員 |
| 実施場所 | 学校の余裕教室や公民館、児童館等 | 小学校(余裕教室・専用施設)、児童館、公民館、借家等 |
| 利用料 | 無料 | 原則有料(保育料、おやつ代等) |
| 提供内容 | 学習・スポーツ・体験活動・文化芸術活動・交流活動等、安全安心な遊びの場 | 家庭に代わる生活の場(宿題、昼寝、食事、遊びなど) |
| 所管 | 国:文部科学省 (学校と地域でつくる学びの未来(文部科学省HP)) 市:教育部生涯学習課 |
国:こども家庭庁 (放課後児童健全育成事業(こども家庭庁HP)) 市:こども福祉部こども課 |
佐野市の放課後子ども教室
形態と特徴
| 形態 | 特徴 |
|---|---|
| 待機型 | ・下校時間が早い低学年の児童が、高学年の児童と一緒に安全に下校できるようにするため、高学年の児童の下校までの時間(1時間程度)に活動します。 ・1年生、1年生と2年生というように、原則としてその学年全員が参加します。 ・放課後子ども教室専用のスペースでなくても、学校の空き教室などを使って活動することができます。 |
| 日常型 | ・子どもたちは参加したい曜日や時間帯を自由に選んで参加することができます。 ・活動のスペースや運営や運営スタッフの人数によっては、定員を定めて参加者を募集することもあります。 ・学校の余裕教室など、放課後子ども教室の専用スペースを確保することが望まれます。 |
| イベント型 | ・週末などに、様々な体験活動やイベントなどを行います。 ・イベントごとに参加者を募集することができます。 ・学校だけでなく、公民館などでも活動することがあります。 |
教室一覧
| 放課後子ども教室名 | 活動場所 | タイプ | 実施回数 | 参加者数 (1回平均) |
実施場所 | 内容 | 活動の様子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いきいき何でも体験クラブ | 犬伏東小学校 | 日常・イベント型 | 57回 | 520名 (9名) |
体育館 他 | ミニバス、自由遊び、ミニミニコンサート 等 |  |
| 旗川小学校区放課後子ども教室 | 旗川小学校 | 待機型 | 17回 | 375名 (22名) |
図書室、空き教室 他 | 読み聞かせ、クリケット 等 |  |
| 石塚小学校区放課後子ども教室 | 石塚小学校 | 待機型 | 65回 | 2,011名 (31名) |
校庭、空き教室 他 | 縄跳び、クリケット 等 | |
| 出流原小学校区放課後子ども教室 | 出流原小学校 | 待機型 | 11回 | 140名 (13名) |
空き教室 他 | 工作、バルーン 等 | |
| 多田っ子広場子ども教室 | 多田小学校 | 待機型 | 21回 | 183名 (9名) |
空き教室 他 | 読み聞かせ、自由遊び 等 | |
| くずう放課後子ども教室 | 葛生義務教育学校 | 待機型 | 16回 | 350名 (22名) |
図書室、空き教室 他 | 化石みがき、マラソン 等 |  |
| どんぐり子ども教室 | 葛生地区公民館 | 日常型 | 16回 | 81名 (5名) |
葛生地区公民館 | 合唱、ミュージックベル 他 |  |
(注意)実施回数、参加者数は令和6年度の実績です。
(注意)各教室に関するお問い合わせは、生涯学習課(0283-20-3109)にお願いします。
運営方法
教室ごとに設置された実行委員会と市が委託契約を締結し、実行委員会により運営されています。
実行委員会は、こどもたちを地域全体で見守るため、運営スタッフ(地域)、保護者(家庭)、学校関係者等で構成されています。
運営スタッフ
(1)コーディネーター
教室ごとに、総合的な調整役を担う「コーディネーター」を1名程度配置しています。
コーディネーターは、保護者等に対する児童の参加の呼びかけ、学校や関係機関との連絡調整、ボランティア等の地域協力者の確保・登録・配置、活動プログラムの企画などを行っています。
(2)協働活動サポーター
教室の参加人数や活動内容に応じて、2~8名程度配置しています。
活動中のこどもの安全を見守り、遊び、スポーツ、文化活動等の交流・体験活動のサポートをしています。
(3)地域ボランティア
必要に応じて地域の方をボランティアとして配置し、活動内容の充実及び地域住民との交流を図っています。
令和7年度佐野市放課後子ども教室交流研修会を行いました
放課後子ども教室関係者等が市内の放課後子ども教室を見学する、放課後子ども教室交流研修会を実施しました。
運営スタッフは、他の教室の活動を実際に見学したり、参加者同士で情報交換をしたりして得られたアイデアを、日々の活動に生かしています。

実施日:11月15日(土曜日)
教室名:どんぐり子ども教室
活動内容:合唱、ミュージックベル

実施日:12月4日(木曜日)
教室名:くずう放課後子ども教室
活動内容:マラソン指導

実施日:12月13日(土曜日)
教室名:いきいき何でも体験クラブ
活動内容:ミニミニコンサート
- この記事に関するお問い合わせ先
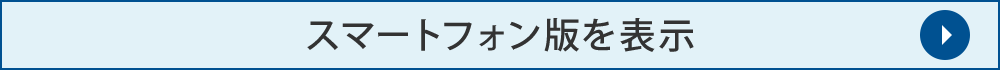











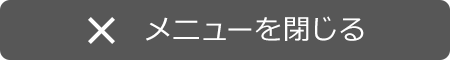












更新日:2026年01月28日