市長の記者会見【令和6年11月5日の案件】
令和6年11月定例記者会見次第 (PDFファイル: 107.2KB)
(1)令和7年度佐野市行政経営方針について
令和7年度佐野市行政経営方針を決定しました。
策定の目的は、第2次総合計画に示す将来像の実現、人口減少社会の克服に向けて、「人とのつながり」を重視するとともに、「デジタルの力」を活用することで、これまでの取組を更に発展させていくことが求められています。
また、地球温暖化による気候変動の影響により、全国各地で頻発する自然災害や近い将来発生が危惧される首都直下地震などへの備えとして、これまでの災害を教訓とした市民の安全安心を守る施策を継続的に取り組むとともに、官民連携、地域間連携による災害対応力を一層高めていく必要があります。
コロナ禍を乗り越え、経済は回復しつつあるものの、物価高騰や金融不安への懸念に加え、人口減少が加速化し、地域経済の縮小や労働人口の減少により社会インフラ及び地域コミュニティの維持が困難になる中、経済社会のグローバル化やデジタル化の急速な進展により様々な分野で国際的な相互依存関係が深まるなど社会環境は大きく変化してきています。
一方で、本市の財政状況は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」においては、健全段階を維持しているものの、人口減少・少子高齢化や市有施設の老朽化などの構造的な課題により、今後非常に厳しい財政運営になることが想定されます。
そこで、これら直面する様々な課題を解決するため、第2次総合計画中期基本計画の施策横断的取組である「コンパクトシティ」「SDGs」「スマートシティ」の推進に向け
・デジタル技術の活用による地域課題の解決
・防災・減災対策、国土強靭化への取組
・少子化対策の取組
・脱炭素社会の実現に向けた対応
・民間活力の導入による行政のスリム化
・集約型のまちづくりの推進
などの施策を展開し、将来にわたり持続可能で強靭なまちづくりを行い、市民生活の質の向上を目指すことを目的として行政経営の基本方針を示すものです。
「行政経営の基本方針」については、第2次総合計画中期基本計画のまちづくりの基本理念である「進化する佐野市」「選ばれる佐野市」の実現や各施策の目標を達成するため、部局間連携による横断的な取組を円滑に進めることを強く意識し、物価高騰等の影響による市民生活や地域経済の下支え、防災・減災対策に加え、自然災害等への迅速かつ柔軟に対応するための「国際防災拠点さの」の取組、子どもたちの明るい未来のための教育と子育て環境の充実や若者が結婚、妊娠、出産、子育ての希望を叶えられる「こどもまんなか社会」の実現に向けた取組、交流人口や経済交流の促進につなげる海外展開を進めるとともに、多文化共生の地域づくりの土壌となる国際戦略の策定にむけた取組を実行するため、4つの基本方針を掲げています。
「(1)効率的な行政経営」では、行政改革大綱及び業務改善計画を推進することで、質の高い行政サービスの提供に向け、社会情勢に見合った行政改革を進めるとともに、受益者負担の適正化、施設の将来更新費用の縮減を図っていきます。
あわせて、再構築を進めている行政経営システムを踏まえて、行政評価等の適切な運用を行うとともに、デジタル技術の活用により、事務の効率化と付加価値の向上を図っていきます。
「(2)持続可能な財政運営」では、歳入については、一般財源総額において、当初予算比で前年度以上を確保できる見込みである一方で、歳出については、財政の硬直化が進んでいる中で、老朽化が進んでいる市有施設への対応、防災・減災対策、多様化・個別化しているニーズへの対応や、新たな課題解決へ向けた取組が求められる中、物価高など社会状況の変化に留意する必要があることから、財源の効果的・効率的な活用を図っていきます。
「(3)職員の能力向上」では、時代や環境の変化に適切、迅速かつ柔軟に対応できる職員の育成を推進し、高度化・多様化する市民ニーズに応えるために職員に求められる能力の向上を図るほか、働き方改革の推進による職場環境の充実に努めていきます。
「(4)市民との協働」では、協働への理解と市民活動への参画を促進するとともに、官民がそれぞれの特性を生かした適正な役割分担と連携により、協働による自治を推進していきます。
令和7年度の取組は、この行政経営の基本方針に基づき、10の取組を進めていきます。重点施策の選定と各施策の取組方針については、「まちづくりの重要認識度評価」「市長公約との直結度」「中期基本計画の施策横断的取組」や「総合戦略」といった全庁共通課題との関連性により、記載の14施策を重点施策として選定しました。
この行政経営方針をもとに、「人とのつながり」を重視するとともに、「デジタルの力」の活用を図り、部局間連携を強化することで、第2次総合計画における将来像の実現に向けた取組を進めていきます。
(2)市民広場駐車場の有料化及び終日利用について
現在、平日夜間閉鎖している市民広場駐車場について、令和7年1月より「出入口ゲート」を設置し、一定時間以降を有料化し、終日利用を可能にします。
終日利用を可能とするにあたり、市役所利用者の駐車に支障のない適正な駐車場の運用を行うため、また、周辺の飲食店等の利用時間も考慮し、入庫後3時間は無料、以降を有料とします。これにより、駐車場利用者の公平性を確保するとともに、目的外や長時間の利用を抑制し、市有財産の有効活用を図りながら、まちなか活性化に寄与します。
有料化および終日利用の開始時期は、令和7年1月6日(月曜日)の午前8時15分からです。駐車料金は、入庫後3時間は無料、以降1時間毎に税込み110円としますただし、市役所利用者で駐車時間が3時間を超え、使用料が発生する場合は、認証機での処理により無料にします。
出入口ゲートについては、現在の出入口と同じ位置に設置します。また、これに伴い出入口ゲート等の設置工事を行います。工事期間は、令和6年12月9日(月曜日)から27日(金曜日)までを予定しています。工事の主な内容は、出入口ゲートバー、駐車券発券機、駐車料金精算機等の設置です。工事期間中は、駐車場の出入口が変更になるとともに、一部対面通行になります。
なお、年末年始の12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)までは、終日無料で開放します。
(3)「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展の開催について
「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展を、令和7年1月25日(土曜日)から3月9日(日曜日)まで、佐野市立吉澤記念美術館で開催します。本展は佐野市制20周年記念特別企画展であり、国立文化財機構文化財活用センターによる「貸与促進事業」として、同センターおよび東京国立博物館の特別協力を得て実現します。
概要は、栃木県の文化財保護に大きな功績のあった考古学者・丸山瓦全が見いだし、保護に尽力した佐野市域の文化財を紹介します。
展覧会の目玉は、重要文化財「エラスムス立像」と、天明鋳物の重要作品で東京国立博物館所蔵の重要文化財「鋳銅梅竹文透釣燈籠」です。
「エラスムス立像」は、佐野市上羽田町の寺院、龍江院で「貨狄様」として保存されていた像に、丸山瓦全が注目し、広く紹介したところ、実は三浦按針(ウィリアム・アダムス)らが乗ってきたリーフデ号の船尾像だったと判明しました。瓦全が国外流出を阻止し、昭和5年に旧国宝になり、戦後は制度改正で重要文化財となりました。大正14年から東京 国立博物館に預けられており、この像の佐野への里帰りは、約100年ぶりとなります。
もうひとつの目玉が、天明鋳物の研究と保護です。丸山瓦全は天明鋳物の研究をしており、近代金工の巨匠・香取秀真と親しく交流していました。本展覧会では、香取秀真が重視し、東京国立博物館に所蔵されている重要文化財の「鋳銅梅竹文透釣燈籠」と、その5年前に制作され、現在も佐野にある同型の燈籠、そして丸山瓦全の依頼で香取秀真が制作し、葛生の吉澤家で保管された「写し」を三つ並べて展示します。
また、展覧会の開催に先立って行った調査により、丸山瓦全のパワフルな文化財保護活動に関する様々な発見・事実も判ってまいりましたので、あわせてご紹介します。
このような丸山瓦全の活動は、佐野市の文化財保護行政の重要なルーツとなっております。本市では近年、「天明鋳物のまちづくり」を推進し、令和5年1月に「天明鋳物」が地域団体商標として登録され、また、令和6年3月「佐野の天明鋳物生産用具及び製品」が国の重要有形民俗文化財の指定を受けました。丸山瓦全の活動をたどることは、現在、本市が進める「天明鋳物のまち」としての取り組みの根本を見つめることになります。
令和7年2月に、市制20周年を迎えるに際して、この展覧会を開催することで、市民が、佐野市の文化財の重要性と市域が文化的につながりが深いことを知り、郷土への愛着を深める機会としたいと考えています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部広報ブランド推進課広報・地域連携係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3037 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら
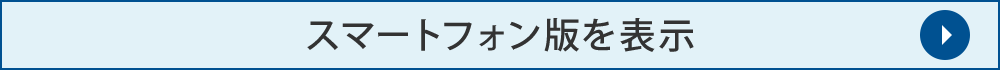











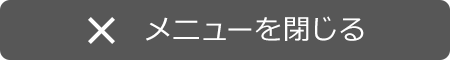












更新日:2024年11月05日