臨時記者会見【令和7年3月12日】
市長説明
3月12日(水曜日)に開催された市議会本会議におきまして、指定管理者制度の在り方調査特別委員会から、最終報告書が提出されたことから、この件に関しまして、私から説明させていただく機会として、記者会見の開催をお願いしました。
まず、100条委員会の委員をはじめ、市議会の皆様には、お骨折りをいただいたことに、感謝申し上げます。報告書の内容につきましては、まだ、詳細を確認しておりませんが、今後、内容を精査した上で、市として改善策を検討してまいりたいと考えております。
なお、調査事項の3点を含め、私の所感を述べさせていただきます。
<募集要項変更の疑義>
報告書によりますと、募集要項の変更は、私の指示によるものと認定されておりますが、私としては、募集要項の変更に係る事務手続の中で、私と職員の間で、誤解や誤認が生じていたものと考えております。
募集要項の変更については、私から指示をしたという認識はございませんが、職員においては指示と受け止め、私と職員との間に、認識のズレがあったものと改めて感じているところです。
今後につきましては、意思決定過程をより明確にし、指示命令や報告事項の違いなどについて、職員との認識のズレが生じないよう、改善を図ってまいりたいと考えております。
次に、そもそも「指示」を行う必要性があるのか?という点につきましては、これまでの証人尋問等からは、要綱を変更することによって、株式会社極東体育施設に対し、何らかの便宜供与が行われたのではないか、という文脈が読み取れます。
しかし、(1)募集要項の変更の有無に関わらず、株式会社極東体育施設は、指定管理選定に参加できたこと。(2)PFIの実績の追加により参加資格を得た「アリーナたぬま」の指定管理選定においては、落選していること。
から、募集要項の変更によって、株式会社極東体育施設に対する便宜供与が認められないこと、かつ、選定委員会は、公平・公正に機能していたと捉えることができるものと考えております。こうした点から、便宜供与がなく、意味が見出せない募集要項の変更指示そのものに、必要性がないのではないかと申し上げたいと思います。
<選定過程の疑義>
選定過程の疑義につきましては、報告書によりますと、選定委員会の委員長である副市長の質疑内容が、当該会議録から削除されたとありますが、こう断定することには疑義が残ります。
執行部といたしますと、副市長の証人尋問における委員からの指摘により、令和5年10月に資料要求に伴い提出した資料と、令和6年3月に本委員会に提出した資料に差異があることを初めて確認したものです。
これは、文書ファイル内に、完成後の会議録と、未完成の会議録の複数のデータが存在していたことによる取違いと、提出時における文書の確認漏れによるものと考えており、指摘されている部分(2行)を意図的に削除した可能性は限りなく低く、文書の取違いにより発生した事務上のミスであると認識しております。
しかしながら、事務上のミスであったとしても、こうした結果をもたらしたことにつきましては、深くお詫び申し上げるところであります。
<当該事業者との関係性の疑義>
当該事業者との関係性につきましては、様々なご指摘をいただいておりますが、募集要項の変更等に関して、私としては当該事業者との間に、疑われるような点はないものと考えております。
<虚偽証言に対する告発>
報告書において、虚偽証言の疑いにより、告発を求められております。
100条委員会での証人尋問において、私としては、誠実に対応してまいりましたが、結果として、虚偽証言の疑いをかけられ、告発されるという事態になりました。私としては、100条委員会に全面的に協力する中、一貫して真実を述べてきたつもりであり、この点につきましては、繰り返しになりますが、募集要項の変更に係る事務手続の中で、私と職員の間で、誤解や誤認が生じていたものと考えております。私から指示をしたという認識はございませんが、職員においては指示と受け止め、認識のズレがあったものと改めて感じたところであります。今後、認識のズレが生じないよう、改善を図ってまいりたいと考えております。
そのほかも幾つかございますが、内容を精査した上で、適正に対応してまいりたいと考えております。
告発につきましては、市政運営に対する信頼に影響を与えかねない問題だと認識しています。しかし、私は市長として真実を示してきており、虚偽証言には当たらないと認識しており、告発に関する議会のご判断・ご意思につきましては、大変、残念に思います。
今後は、市民の信頼を回復するために全力を尽くしてまいりますとともに、このような事態に対し、透明性のある対応を行うことが重要だと考えております。
今後どのような対応が必要になるのか、弁護士と詳細について相談した上で、私が誠実に証言したことを証明するため、必要となる対応をしてまいりたいと考えております。
<第三者による調査>
第三者による調査についてでありますが、市議会が設置をした100条委員会での調査と、市執行部が行う第三者による調査は、どちらも調査や問題解決を目的としていますが、それぞれ異なる役割と性質を持っております。
100条委員会は、議会としての責任において行政を監視し、必要な場合には強制力を伴って調査を進めます。一方、市の第三者による調査は、公正かつ専門的な観点から専門家により問題を分析し、解決策を探るものです。あくまでも事務執行上の改善を図るものであり、手続きとしては、議会軽視には当たらないと考えております。
まずは、最終報告書の内容を十分に確認し、改善策を策定することを最優先に取り組んでまいりたいと思います。そして第三者による調査は現時点では私は白紙と考えております。
検証が必要な事項につきましては、庁内で論点を整理し、その上で、新年度において、改めて検討が必要だと思っております。
<市民の皆様へのメッセージ>
最後に、市民の皆様にお伝えしたいのは、今回の件では、本当にご心配、またご迷惑をおかけしてしまったこと、大変申し訳ありません。私は、真実を述べたと誠実に信じており、その信念は今も変わりません。
市民の皆様の信頼を回復するためには、引き続き、市政運営に全力で取り組んでまいりますので、今後の対応を見守っていただけますようお願い申し上げます。
<田中弁護士の補足説明>
弁護士の田中と言います。市長の代理人として、100条委員会では「補佐人」として立ち会っていた立場から、若干補足説明させていただきます。
まず、今回「偽証」ということで告訴、告発されるという話になっていますけれども、今回の市長の、議会が指摘する「指示をしていない」という部分については、市長の記憶に基づいた証言になっていますので、これは偽証にあたりません。
若干法律的な説明をいたしますと、偽証については2説ありまして、「客観説」と「主観説」とがあります。「客観説」は、「真実に反することを証言することが偽証だ」という立場。それから「主観説」は、「自分の記憶に反することを言うことが偽証だ」という立場がありまして、自分が、例えば記憶で、「Aという人が犯人だ」と思っていても、いろんな事情を考えると、Bという人が犯人と推測されるという考えを持った場合に、「犯人はA」と証言をすれば、主観的な記憶と合っているので偽証には当たりませんけれど、真実、Bが犯人だったとしても、「B」とその人が主張すると偽証に当たると。そういう学説的な話がございます。
裁判例で取っているのは主観説になりますので、仮に客観的事実と反することがあったとしても、自分の記憶に従った証言をしないと、それは偽証だと捉えられることになります。ですから、このケースでは、市長は真実に従って、自分の記憶にのっとって証言をされていますので、偽証には当たらないということです。
それと、今回の100条委員会では、議会側に弁護士さんがついてらっしゃったと思います。告発についても、おそらく法的なアドバイスを受けていらっしゃると思うんですね。おそらくこの「主観的真実」という説明についても行われていると思います。そうすると、その説明を聞いた上で、あえて告発という話になった場合には、逆に不当な告訴、告発罪、そういう別の犯罪類型がありますので、そういった犯罪に抵触する危険性があるんじゃないかということを感じております。
それと、今回の疑念というのは、市長と極東の関係性から、3施設について、極東が契約を締結し、短期間で破産してしまったと。そのような「市長との便宜供与的な動きがあるんじゃないか」という話を発端にしているかと思うんですけれど、この3施設に関して説明しますと、当初の募集要項には、実績等の募集要件は存在してなかったんですね。ですから、言い方をざっくり言うと、「誰でも応募できた」わけです。ところが、変更後の中身には2つの募集資格が加えられて、1つは、複数の体育施設を運営した実績があると、運営実績。または、PFI、これを行ったことがある実績、という2つを入れているわけです。
ですから、市長としては、当初の募集要項は、「誰でも応募できる」という観点からすると、あえて要項を変更して、極東に便宜を供与する必要性が全くなかったわけです。ですから、そこの部分について便宜供与があったという疑いを持たれてると。それについては、市長としては全く必要性がないことで、「なぜ指示をして要件を変更しなきゃいけなかったんですか」という、単純素直な疑問が出てくるんですね。
一番わかりやすいのは、もう直接、随意契約を結べばいいわけです。「極東と随意契約を結べ」と。それだったらはっきりするわけですけれど、この要件の変更というのは、そういう運用実績であるとか、PFIの運用実績であるとか、そういったこの事業を運用するのに適切な資格要件を定めて出しています。その中で、市長が便宜供与しても、それは全く当初の、全く何も資格制限のない要項からすると、「便宜供与に当たる」という出発点がそもそも間違いだろうと判断しています。
それと、私が補佐人として関与してきた中での話ですけれど、100条委員会の結論がどうだったとしてもですね、今回「証人尋問」という形で行われているわけですが、その基本としては「人権に配慮した形でやってくださいよ」という話になっていて、運用の中では「1人1回につきおよそ60分」という定めを自ら出していたと。ところが、こちらの体調とか、そういったことも確認しないで、何度も延長ということで長時間に渡って質問を繰り返すと、そういう事態があったことは、私からすると、「人権配慮に欠けた運用だったんではないか」と思います。「途中で体調悪くして倒れられたら、委員会はどう責任を取るんでしょうか」という疑問がありました。
それともう1つは、この100条委員会の質問については、民事訴訟法の証人尋問のところを準用して使うことになってるんですけれど、それは基本として「事実を聞く」ということになってます。事実を聞く。「無用な重複尋問は行わない」ということが定められています。皆さんお聞きになったと思いますけれど、委員の方は、自分の意見を言って、「それに反してるんじゃないか」という聞き方をされたり、それから、同じような点を繰り返しされて、「いい加減に認めないんですか」みたいな話をされて、それが、この件に関しては、市長に関しては、公開の場で長時間にわたって責められている。これは、私からするとちょっと人権に配慮していない、そういう運用が行われていたなと感じています。
今後、100条委員会というものが開催されることがないことを祈っておりますけれど、同様のものが起こった場合には、ぜひその辺は考慮された運用をされるようお願いしたいなと感じております。以上です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部広報ブランド推進課広報・地域連携係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3037 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら
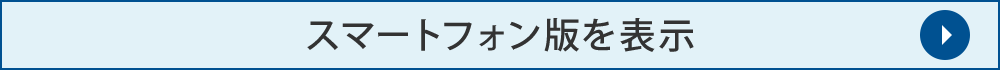











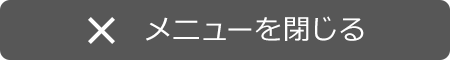












更新日:2025年03月14日