退職所得に対する市・県民税の特別徴収について
退職所得に対する市・県民税の課税
退職所得とは、退職により勤務先から一時に支払いを受ける退職手当や一時恩給などです。
個人の市・県民税は前年中の所得に対して翌年課税するのが原則ですが、退職所得に対する市・県民税については、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を特別徴収し、申告納入していただくことになっています。
納税義務者
退職手当等の支払を受ける人で、その受けるべき日(通常時は退職日)の属する年の1月1日現在、佐野市に住所がある人です。
計算方法
1. 退職所得の金額を求めます
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
=退職所得の金額【課税標準】(計算後、千円未満を切り捨て)
| 勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円) |
| 勤続年数が20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります 。
役員等(注1)以外の方で、勤続年数5年以下の方の場合、支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象になります。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。
詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
(注1)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
2.税額を求めます
退職所得の金額【課税標準】×税率(市民税6% 県民税4%)
=特別徴収すべき税額(計算後、市民税・県民税それぞれ百円未満を切り捨て)
計算例
勤続年数25年で、退職手当等15,313,633円の場合(役員等の期間がない場合)
退職所得控除額
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
退職所得の金額
(15,313,633円-11,500,000円)×1/2=1,906,816.5円【千円未満切り捨て 1,906,000円】
市民税の特別徴収すべき税額
1,906,000円×6%=114,360円【百円未満切り捨て 114,300円】
県民税の特別徴収すべき税額
1,906,000円×4%=76,240円【百円未満切り捨て 76,200円】
徴収した税額の納入
退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに税額を納入書により指定金融機関等へ納めていただきます。その際に、「市民税・県民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています。)への記載をお願いいたします。
同時に2名以上の退職所得に対する市民税・県民税の徴収がある場合には、徴収した月の翌月10日までに「退職所得に係る住民税納入内訳書」を利用して市民税課まで提出してください。
「退職所得に係る住民税納入内訳書」はダウンロードできます。
納入期限
特別徴収した月の翌月10日です。
(注意)土曜日・日曜日、祝祭日の場合は翌開庁日となります。
納入書が必要な場合は市民税課までご連絡下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部市民税課市民税係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら
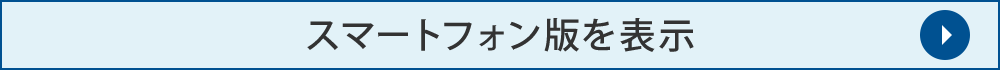











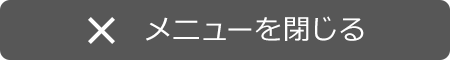












更新日:2024年11月20日